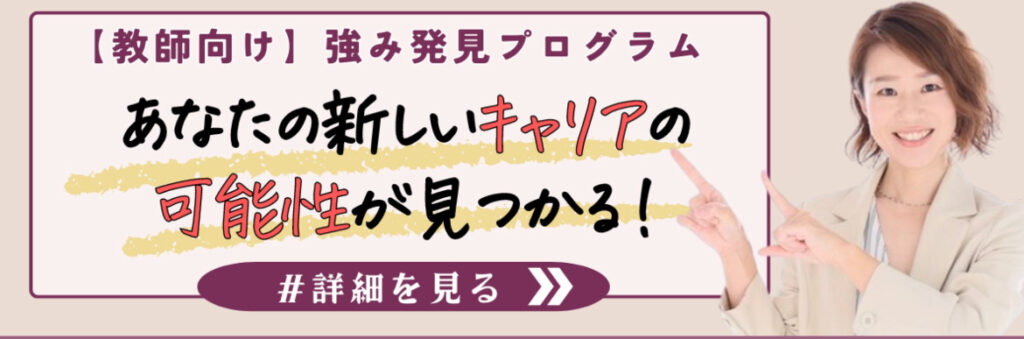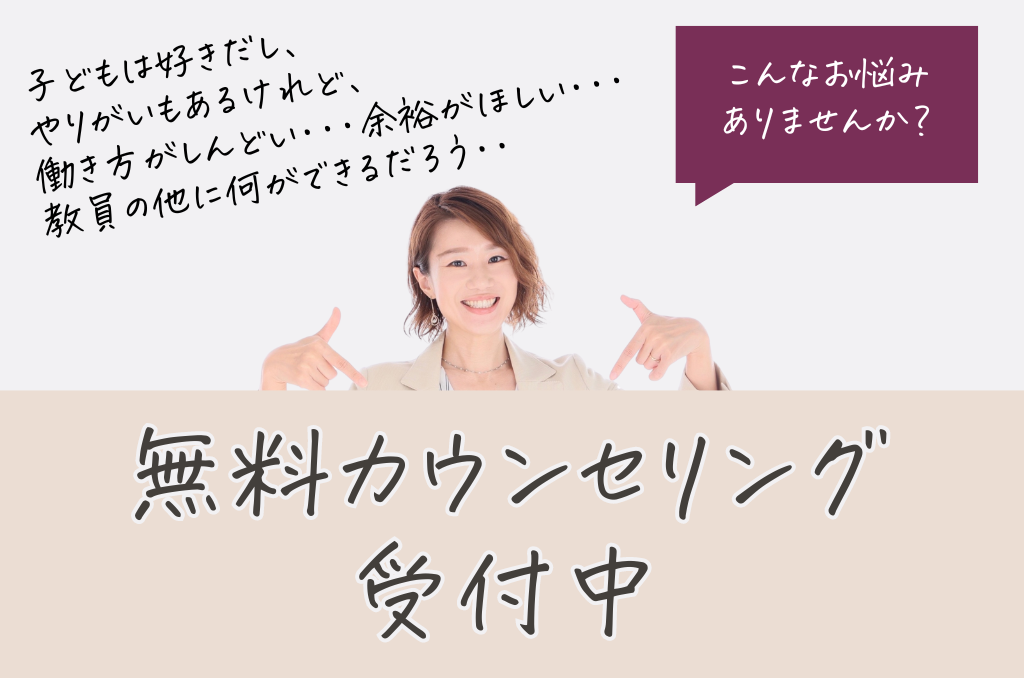9年間の教員実績があるからこそ、留学を決断できた!私が見つけた「自分らしい生き方」
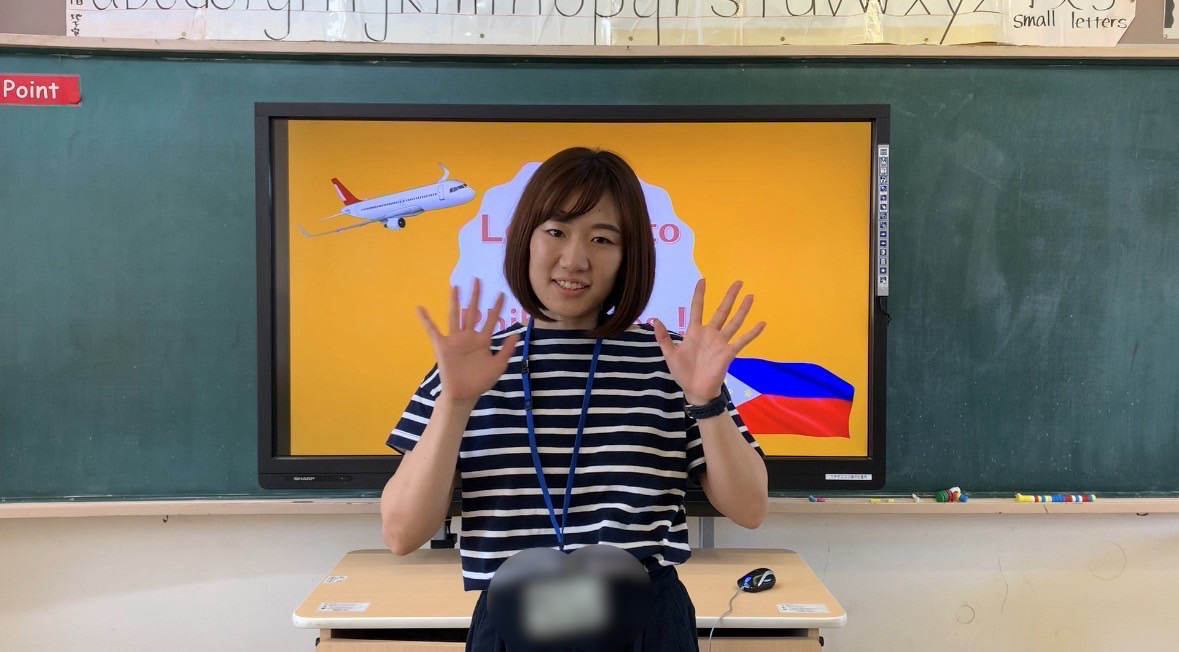
新川:
あやかさん、今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします!本日はよろしくお願いします。
ーあやかさん:
よろしくお願いします。
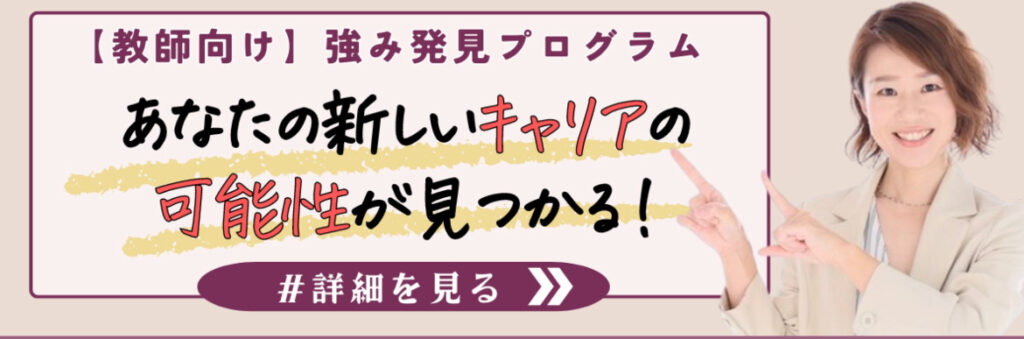
プログラム終了時
新川:
まずは、簡単な自己紹介をお願いできますか。
ーあやかさん:
はい。私は公立の中学校と小学校で合わせて9年間、外国語専科として主に英語を教えてきました。実は大学時代から漠然と「いつか海外で生活してみたい」という思いを抱いており、2024年3月末で教員を退職し、今は約半年間かけて準備してきた、念願の留学に向けていよいよ出発するところです。
新川:
9年間といえば、社会人として一定のキャリアを積んだ期間ですよね。その積み重ねを手放して新たな一歩を踏み出すには、相当な覚悟を要したのではないでしょうか。そもそも教員としてのスタートは、中学校からだったそうですね?
ーあやかさん:
そうです。最初は中学校で英語科の教師として採用されました。当時は新卒で、右も左もわからない中でのスタートでしたね。
新川:
教員になった当初、迷いはありませんでしたか?教育学部出身というわけでもなかったんですよね。
ーあやかさん:
はい。私は大学で国際系の学科に所属していて、学生時代は、旅行会社や航空会社など、海外と関わりのある仕事に興味を持っていました。ただ、親戚に教員経験者が多いこともあって「先生は安定した職業」というイメージが私の中に刷り込まれていたんだと思います。正直なところ、「教員が自分の天職だ!」という強い使命感があったわけではなかったんです。就職活動は民間企業も受けましたが、うまくいかず、「もし教員採用試験に落ちたら、思い切って留学しよう」というある意味逃げ道のような考えも頭の片隅にありました。でも、運よく(という言い方も変かもしれませんが…)試験に合格したので、「とりあえず、この道に進んでみようかな」と教員になった、という感じなんです。
新川:
なるほど。大学時代から海外に興味があったという点が、後の留学志向にもつながっているようですね。中学校で教師生活をスタートした後、小学校でも教えたのはなぜでしょう?人事異動ですか?それともご自身の希望でしょうか?
ーあやかさん:
自分から希望しました。中学校はとにかく業務が多岐にわたり、特に部活動指導や受験指導は時間的・精神的な負担が大きかったんです。当時は「辞める」という選択肢は全く頭になくて、「どうにかして、この苦しい状況を打破できないか?」と、本当に毎日悩んでいました。そんな中、たまたま初任者研修の一環で、小学校で英語の授業をする機会があったんです。そこで子どもたちが本当に楽しそうに、目をキラキラさせながら、英語を学んでいる姿を目にしました。「働く場所を変えることで、自分自身も、もう少し前向きな気持ちで、子どもたちと向き合えるかもしれない」そう思い、小学校への異動を希望することにしました。

新川:
小学校では外国語専科として働いたとのことですが、その環境はどうでしたか?
ーあやかさん:
小学校は小学校でまた違う苦労がありました。私が勤めたのは千人以上の児童がいるマンモス校で、専科教員はクラスを持たない分、様々なサポート要員として駆り出されることが多かったんです。例えば、運動会や宿泊学習などの学校行事の準備はもちろん、まだ20代で若手だった私は、「ここは自分が動かなきゃ…」と、いつも周囲の空気を読みながら、率先して雑務を引き受けるようにしていました。さらには、手が足りない時には、1年生や2年生のクラスの補助に入ることもありました。中学校時代の、常に時間に追われるような「激務」とは少し違いましたが、学校内の独特な文化や、先生同士の人間関係など、目に見えない部分での調整力が求められる場面が多く、精神的にはかなりすり減っていたように思います。
新川:
中・小と両方経験したことで、教育現場の多面性が見えてきたのでは?
ーあやかさん:
そうですね。「大変さ」という言葉一つ取っても、中学校と小学校では質が違うんです。中学校は、とにかく部活動と受験指導が大変でした。毎日のように朝早くから夜遅くまで、部活動の指導や、授業の準備に追われ、肉体的にも、時間的にも、常に何かに追い立てられているような感覚でした。
一方、小学校では、部活動や受験指導がない分、肉体的・時間的には余裕があった部分があったかもしれません。
でも、例えば、1年生のクラス補助で、まだ学校生活に慣れていない子どもたちの面倒を見たり、職員室で「若手の先生は、もっとこういう風に動くべき」といった、言葉にはされないけれど、何となく感じる無言の圧力があったり… 若手ならではの気遣いや、立ち回りが求められることが多く、精神的な「空気読み」スキルが、中学校以上に必要とされる場面が多かったように思います。その結果、中学校と小学校、「どっちが楽」ということは全くなく、働く場所によって、求められる能力や、働き方が、本当に大きく変わるんだと、身をもって痛感しました。
新川:
3年間小学校で頑張った後、再び中学校へ戻ったんですよね。
ーあやかさん:
はい。一度小学校を経験したことで、中学校の、良くも悪くも分業制で、先生一人ひとりの役割がはっきりしている環境が、自分には合っているのかも、と思えるようになったんです。もちろん、中学校の部活や受験指導の大変さは、身に染みて分かっていました。でも、小学校での経験を通して、「もしかしたら、自分の意識や、働き方を少し変えることで、中学校でも、もう一度頑張れるかもしれない」と、前向きに考えられるようになったんです。
新川:
しかし、最終的には退職を決断したのは、どんな出来事が契機になったのでしょうか?
ーあやかさん:
中学に戻った直後、幼なじみが病気で亡くなってしまいました。コロナ禍で会えないままのお別れで、精神的なショックが大きかったんです。それを機に、私の中で「自分は本当に何のために頑張っているのか?」という問いが噴き出しました。子どもたちに厳しく当たってしまったり、自分を追い込んでしまったりと、教えることが本来の喜びからかけ離れていく自分に戸惑いました。そんな時、コーチングセッションを受けて「自分のダメな部分も受け入れる」「自分を大切にする」という発想に出会ったんです。その瞬間、「一度、この長いマラソンから離れて、自分自身を休ませるのもアリだ」と思えるようになりました。

新川:
コーチングが分岐点になったわけですね。その後、退職と留学という方向に舵を切り、さらに私が提供しているSSプログラムにも参加されましたよね。
ーあやかさん:
はい。退職は決めたものの、「じゃあ私は何をしたいんだろう?留学して何を得たいんだろう?」という、具体的な次のステップについては、まだ明確な答えが見えていませんでした。そんな時に参加したSSプログラムでは様々なワークや、新川さんとの対話を通して、これまで見過ごしてきた自分の強みや本当に大切にしたい価値観に気づけたんです。すぐに、具体的な「ゴール」が見つかるわけではないけれど、「自分にとって、本当に大事なものは何なのか」という、いわば人生の「コンパス」を手に入れる、そんな貴重な時間だったと感じています。
新川:
4ヶ月の受講を経て、具体的にはどんな変化を実感しましたか?
ーあやかさん:
まず自己否定が薄れました。これまで「教師なんて」と思いがちでしたが、SSで強みを再発見する中で「自分も周囲に影響を与えてきたんだ」と認められるようになったんです。教職を離れるときも、漠然とした不安はあったのものの、「ここまでよく頑張った、自分なりに意味のある9年間だった」と前向きに捉えられました。そのおかげで退職後、留学準備期間に入ってから、人がわざわざ会いに来てくれたり、応援メッセージをくれたりするのを「ありがたいな」と素直に受け止められるようになったんです。
新川:
なるほど。それまで漠然としていたご自身の価値が、明確に認識できるようになったのですね。では、いよいよ留学へ旅立つ心境を聞かせてください。
ーあやかさん:
まだ「これをやる!」と確固たる目標があるわけではないですが、自分なりの価値観や指標を手にしたことで、留学という未知の世界に飛び込むこと自体が楽しみになりました。まるでお守りを持って冒険に出るような気分です。何が待っているかわからないけれど、自分の軸があるからこそ、迷っても戻ってこられる安心感があります。
新川:
その安心感があると、挑戦すること自体が前向きな行為になってきますね。今日はありがとうございました。留学先での報告も楽しみにしています。
ーあやかさん:
こちらこそ、ありがとうございました。頑張ります!
後半インタビュー:留学開始から半年後

新川:
あやかさん、お久しぶりです。SSを修了してから約半年が経ちましたが、今はカナダで過ごしているとお聞きしました。現地での生活はいかがですか?
ーあやかさん:
はい、おかげさまでカナダに来てから半年が過ぎました。当初の計画通り、現地に来てから専門学校を選ぼうと思っていたので、最初の3ヶ月は語学学校に通いながら様々な学校を訪問したり、説明会に参加したりして、情報収集に励みました。その結果、最終的に「ホスピタリティ&ツーリズム」のコースがある専門学校で学ぶことにしたんです。実は、日本にいる時は、デジタルマーケティングの分野にも興味があり、どちらの道に進もうか、かなり迷っていました。でも、実際にカナダで、ホテルや観光施設で働く方々から、直接お話を伺ったり、現地の旅行業界の様子を見たりする中で、「やっぱり、私は、旅や、おもてなしに関わる仕事がしたい!」と、自分の気持ちがはっきりしたんです。
新川:
現地で感じる肌感覚が、学校選びや進路決定に役立ったわけですね。SSで得た「自分との対話」は、その後どう生きていますか?
ーあやかさん:
9月頃、ホームシックや天候不良、仕事がまだ見つからない不安が重なって少し落ち込んだことがありました。意味がないことはわかっていても、他人と比較して、「自分はダメだ」と一瞬迷走しかけたんです。でもそのとき、SSの資料や自分がまとめたノートを見返して、「私はこういう価値観を大事にしている」「これまでこんな頑張りがあった」という事実に立ち戻れたんです。「自分は大丈夫、今は一時的につらいだけ」と踏みとどまることができました。
新川:
「戻れる場所」があるって、とても大きいですね。今後はどんな目標や挑戦を考えていますか?
ーあやかさん:
正直、まだ「これが私の人生の最終目標!」と胸を張って言えるようなものは、まだ見つかっていません。でもカナダに来て、自分の力で生活していく中で、「自分で稼ぐ経験をしてみたい」とか、せっかくカナダにいるのだから、「この貴重な経験をブログで発信してみたい」といった興味は膨らんでいます。さらに、教員時代に培った英語力を活かして、オンラインで英会話レッスンを提供することも考えています。今は、何か新しいことに挑戦しようとする時、SSプログラムで明確にした、「自分は、こういう時にやりがいを感じる」「こういう環境なら、イキイキと働ける」といった、自分の価値観を、一つの判断基準にできているので、以前よりも、迷いなく軸がぶれにくくなった気がします。
新川:
他人の価値観や一時的な流行に流されず、自分のコンパスに従えるのは強いですね。最後に、似たような悩みを抱える人、特に留学や転職、退職に踏み出せず不安を感じている人たちへのメッセージをお願いします。
ーあやかさん:
人生を大きく変える魔法の方程式はないかもしれません。私自身も、教員を辞めたからといって劇的に世界が光り輝いたわけではありません。でも、SSプログラムを通して、そして、このカナダでの生活を通して、自分と向き合い「これが私の大切にしたいことなんだ」という、いわば「自分の軸」をしっかり持つことができれば、たとえ、ひどく落ち込むようなことがあっても、必ず、また前を向いて歩き出すことができると私は信じています。うまくいかない時期はどんな人にもあるし、私もまだ試行錯誤の真っ只中です。しかし、その手探りで進む過程ですら「自分らしさ」を再確認するチャンスなのだと今は思えるようになりました。だから、自分を責めすぎず、少しずつでも前に進んでほしいです。迷ったら戻れる「軸」を自分の中に持っておくと、将来どんな道に進んでも自分を見失わずに自分らしく生きていくための、大きな助けになるはずです。
新川:
とても力強く、温かいメッセージですね。今まさに奮闘中のあやかさんの言葉だからこそ、説得力があると思います。これからのご活躍も楽しみにしています。
ーあやかさん:
ありがとうございます。報告できるような成果を積み重ねて、またお話しできればと思います。
今回はあやかさんのインタビューをお届けしました。現在奮闘中のあやかさんの言葉には、一つ一つ熱がこもり説得力があるように感じます。
あやかさんはブログも運営しているようなので、気になる方はぜひ覗いてみてください。