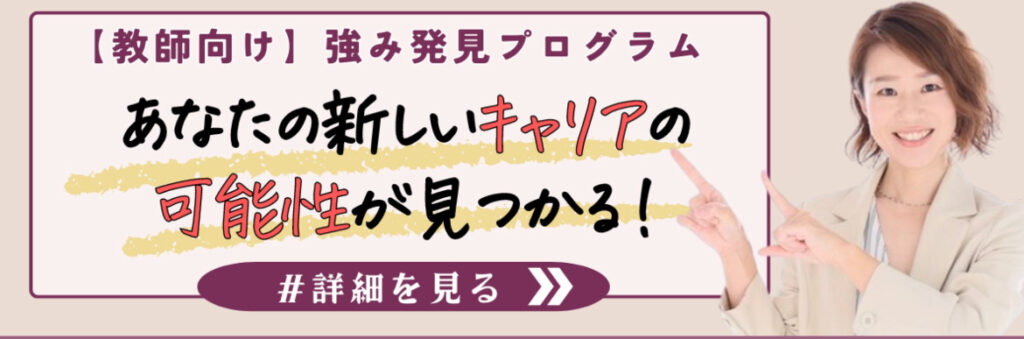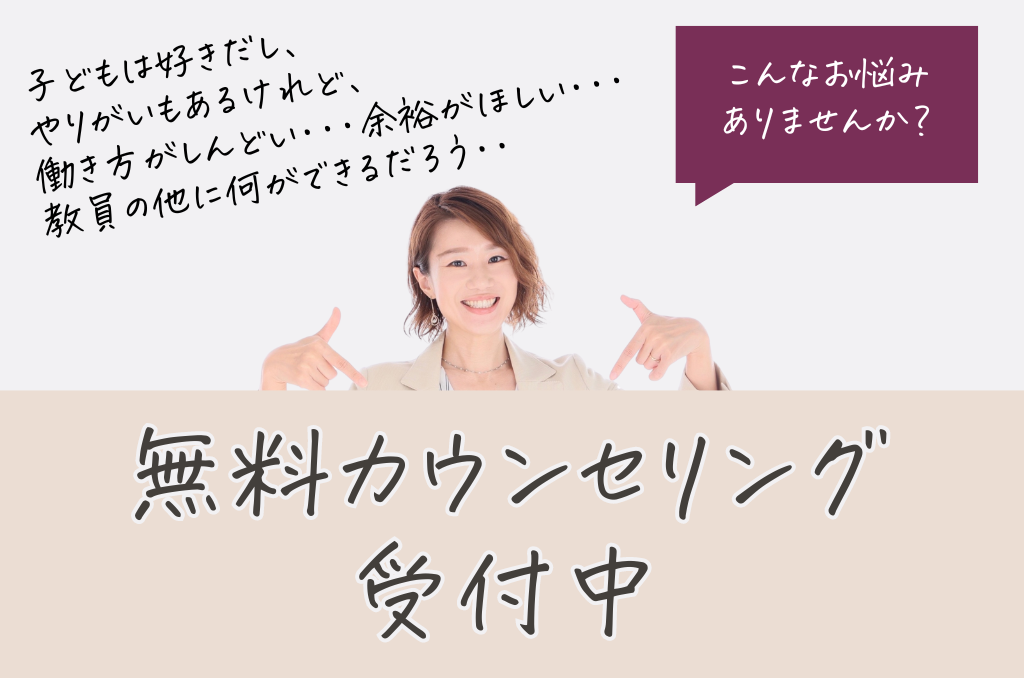教員を続けるか迷った私がたどり着いた、“すぐに辞めなくてもいい選択”

新川:
あみさん、こんにちは!今日はお時間いただきありがとうございます。インタビューよろしくお願いします。
ーあみさん:
こんにちは、お願いします。
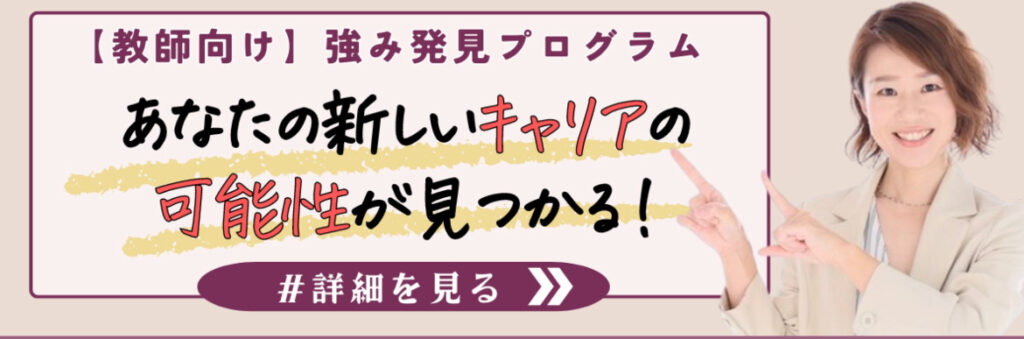
新川:
まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか?
ーあみさん:
あみです。今、37歳で関西の小学校に勤めています。新卒で教員になって以来、ずっと小学校で働いています。途中で産休・育休を挟んでいる話は後ほどさせていただけたらと思いますが、トータルで見ると教員歴は今年度で13年目くらいですね。
新川:
13年目ともなると、お忙しい時期ですよね。2回産休を取られているということで、そのお話も後ほど聞かせてください!ではこれまでどんな先生生活を送ってこられたのかなどについて、SSプログラムを受講するまでの経緯を教えていただけますか?
ーあみさん:
はい。これまで13年の間に異動を2回しています。1回目は最初に採用された自治体の中での転勤で、2回目は採用試験を受け直して、他の自治体に移りました。なので今いる学校は3校目になります。
その間に、2校目と3校目でそれぞれ産休・育休を1年ちょっとずつ、計2回取りました。
SSプログラムに入会したのは、ちょうど2回目(つまり2人目)の育休明けの直前です。4月に復帰だったんですけど、その直前に「このまま復帰するのは不安だな」という思いがあって、3月からSSプログラムを受講しました。

新川:
なるほど。1人目の産休・育休後にいったん復帰して、また2人目を産んで再度育休を取って、もう一度復帰するぞ!というときですね。連続で休まれる方も多いと思いますが、あみさんの場合は一度戻ってからまた産休に入っているわけですよね。そこには色々大変さもあったんじゃないでしょうか?
ーあみさん:
そうですね。連続で産休・育休を取得しているケースも少なくないと思いますが、私の場合は、1回目の復帰のときに自治体をまたいで採用試験を受け直した関係で、採用の時期が決まっていました。まったく新しい職場に新規採用扱いで入ったんです。
子どもが生まれたという家庭環境の変化もあれば、自治体も学校も変わっているという職場環境の変化もあって、とにかく不安要素だらけでした。制度も事前に色々調べて「部分休業を使えるか」を交渉して行使したんですけど、当時の職場では「他にそういった育児の制度を使っている先生がいない」という感じで、早く来て早く帰る私がすごく浮いちゃって。誰とどう話していいかも分からないし、打ち解ける相手もいないしで、そこが一番つらかったですね。
新川:
なるほど。誰も同じような働き方をしていないと、「私ってどう思われてるんだろう」って不安になりますよね。そのうえ家庭に帰れば子育てが待っているわけだし、持ち帰り仕事も多かったでしょうしね。
そういう経験を経て2人目を産んでから、また復帰しようというときにSSプログラムに参加されたわけですね。そのときは「また同じようになるかも」みたいな不安が強かったんですか?
ーあみさん:
はい。1人目の復帰のときも相当しんどかったし、2人の子どもを抱えて同じことをやるのは難しいだろう、と。育休の後半は何か変えなきゃと思って本を読んだり、自己啓発系のワークをしてみたり、強み診断テストを受けてみたり。でも、どうもしっくり来なくて、「自分ひとりじゃ整理できないな」と思っていたんです。
それでいくつかプログラムやコーチングの無料相談を受けたりしたんですが、いまいち「わかってもらえないな」と思うこともあって。そんなときにインスタを見ていたら、新川さんの投稿に出会い、「教員の働き方を変える」「辞める・辞めないも含め、自分の道を選ぼう」という内容が書いてあって、「あ、これだ!」と思ったんです。
新川:
嬉しいです!そこでSSプログラムに申し込んでいただいて、実際4ヶ月受講されてみて、どんな変化や発見がありましたか?
ーあみさん:
一番は「自己理解するのがこんなに面白いんだ」ということです。自分の価値観や強みを棚卸ししたり、何が好きなのか・嫌いなのかを改めて整理したりする作業が、想像以上に楽しかった。あとは、「辞めたほうがいいのか、そうじゃないのか」を即決しなくていいんだ、と気づけたのも大きい。
「教員を辞めたいわけじゃない、でもこのままだとキツいしどうしよう?」というモヤモヤが、SSプログラムを通して「辞める・辞めない」どちらでもいいけど、ちゃんと選べる自分になろう、みたいに変化したんです。「今すぐ辞めなくても、いつか辞める道も用意しておけばいいし、無理に辞めなくてもいい」という感じですね。

新川:
なるほど。すばらしい気づきですね!実際、その後4月に復帰されて、いまは教員を続けながら将来を考えている感じなんでしょうか?
ーあみさん:
そうですね。いまの職場に復帰してみたら、制度や体制がちょっと変わっていて、前回の復帰よりは働きやすさが増していたんです。私は特別支援学級の担任をしているのですが、学級数が増えたことで、担任教員数も増えて、私だけが必死に抱え込まなくてもいい状況になったり。そうした職場環境の違いもあって、「あれ、意外といけるかも」という気持ちになりました。
それと、SSプログラムで自分が「しっかり準備して納得してから行動したい」タイプだとわかったので、急いで辞めるのではなく、例えば「上の子が小学校に上がるタイミングで働き方を変えようかな」とか、そういう中・長期的な計画を立てようと思えるようになりました。
新川:
環境やあみさん自身のものの捉え方も変わったんですね。
今後はどんな形で教育に関わりたい、あるいは、何かやってみたいことがあるんですか?
ーあみさん:
SSプログラムの終盤に言語化できたのは、「子どもたちがやりたいことを伸ばす手助けをしたい」という気持ちです。特に今は特別支援学級でいろんな子の個性や特性を見ているので、もっと多様な学習スタイルを用意できる場があってもいいんじゃないか、と考えたりもして。学校ってどうしても指導要領の枠があるので、子どもたちの個性が十分に活かしきれないこともあります。
それでフリースクールとか体験学習、自然体験などの場に興味があって、少しずつ情報収集しています。あとは大人向けのコーチングを学び始めていて、悩む先生方へのサポートも視野に入れています。

新川:
そうなんですね。特別支援の経験や、自分自身が子育てをしながら働いてきた視点が、今後の活動に生きてきそうですね。最後に、同じように「教員だけど、この先どうしよう」「働き方を変えたいけど辞めたいほどでもないし…」と悩む先生たちにメッセージがあればお願いします。
ーあみさん:
はい。「辞めるか、辞めないか」の二択だけで考えるのって、結構苦しいと思うんです。でも、どちらでもいいし、いつでも選べる準備をしておくと心が楽になる。実際に制度も意外と使えるし、周囲とぶつかることもあるけど、自分が「これを使う」と決めたら案外なんとかなるものだ、とも思いました。
あとは自分だけでモヤモヤしていると同じところをぐるぐる回ってしまうので、SSプログラムのような学びや、誰かに話す場所をつくってほしいです。「今の職場が合わないから辞めるしかない」ではなくて、「まず自分が何を大事にしたいのか」を知るところから始めると、見える世界が変わる気がします。
新川:
ありがとうございます。自分の価値観や強みをはっきりさせておくと、働き方や辞める・続けるの判断にも納得感が出ますよね。今日は貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。
ーあみさん:
こちらこそ、ありがとうございました。今後もいろいろ挑戦していきたいので、進捗があればまたお伝えしますね!